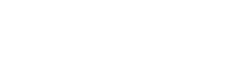ヨーロッパの建物は、窓が小さく、そのため建物の中は暗く、寒いという構造上の欠陥を抱えており、それがゴシック様式の登場によって解消された、という話が下記動画でありました 文献1。
経緯を調べてみたら面白かったので紹介します。
建物の窓が小さかった理由
ゴシック様式以前の建物の窓が小さいのは理由があります。
日本の木造建築では、まず柱を立てて、その上に屋根を乗せ、最後に必要な個所に壁を作るという構造になっています。柱が建物の重さを支えているため、寝殿造の建物に見られるように、御簾などで空間を仕切るだけでもよく、壁そのものは必須ではありません。
他方、寝殿造と同じ時代のロマネスク様式と呼ばれる建物は、まず石造です。石を積み上げ、モルタルで固めた壁で屋根や建物の荷重を支える構造になっています。より大きなものを作るには分厚くしっかりと固めた壁が必要になります。そのため壁に窓を作る=穴をあけるということは強度が落ちるということとトレードオフになり、大きな建物では小さな窓しか作れなかったと考えられます。
ロマネスク様式建築の例:ドイツ・ボン近郊のマリア・ラーハ修道院(画像出典:Donar Reiskoffer, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons)。窓は壁の一部分だけで、小さい。
ゴシック様式の技術革新
12世紀末、日本では平安時代の末期に、のちにゴシック様式と呼ばれる建物が登場します文献2。
端的に言えば、柱に建物の加重がかかるようになり、壁が建物を支える必要がなくなったため、大きな窓を開けることができるようになったのですが、なぜ同じ石造なのにそのようなことが可能になったのでしょうか?
尖頭アーチ
1つ目の技術は尖頭アーチというアーチの登場です。
それまではアーチといえば半円アーチでした。アーチは上部からの荷重を両サイドに逃がす構造ですが、その両端のアーチ支点にはアーチの外側に向かって力が加わります(スラストというそうです文献3)。アーチ支点が外に動いてしまうと、アーチは崩れてしまうため、アーチの左右から動かないように抑え込む必要があります。このためアーチにはそれ以上に大きく丈夫な壁が必要になります。
尖頭アーチは半円よりもとがった形をしています。荷重を両サイドに逃がすのは同じですが、力の向きが垂直方向にむき、外側に崩れる力のスラストは小さくなります。しかもアーチの先端が尖ればとがるほどこのスラストは小さくなります。つまり同じ横幅のアーチであれば、高く鋭いアーチにすることで左右に広がる力は小さくできるようになりました。
 尖頭アーチの例:アーチのてっぺんが尖っている(画像出典:Benjamín Núñez González, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons)
尖頭アーチの例:アーチのてっぺんが尖っている(画像出典:Benjamín Núñez González, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons)
リブヴォールト
2つ目の技術はリブヴォールトとよばれる天井の登場です。
そもそもヴォールトって聞きなじみがない言葉ですが、日本語では穹窿(きゅうりゅう)といいます。もっと知らない言葉になってしまいました。。。要はアーチをつなげてかまぼこ型になっている天井のことだそうですが、穹窿よりはヴォールトのほうが読みやすいのでヴォールトでいきます。
ヴォールトもアーチ技術の延長なので、上部の荷重を両サイドに逃がします。この時左右のアーチだけでなく、前後方向も同じようにアーチを作ると、4つの支点で荷重を支えることができます。これを交差ヴォールトと呼びます。4つの支点で荷重を支えることができるということは、つまり壁ではなく柱で荷重を支えることができるということです。この交差ヴォールトはロマネスク様式から引き継いだ技術です。
 交差ヴォールト画像(画像出典:CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons)
交差ヴォールト画像(画像出典:CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons)
リブヴォールトは交差ヴォールトの荷重を支える稜線に石のリブを加えて補強したものや、さらには荷重を支える石のリブ以外の個所を石材より軽量なレンガや漆喰にしたものです文献4。この結果大きな天井を、4つの支点=柱で作ることができるようになりました。
 リブヴォールトの図解(画像出典:文献4)
リブヴォールトの図解(画像出典:文献4)
フライングバットレス
3つ目の技術はフライングバットレスと呼ばれるはりです。
これまでの技術で天井を壁ではなく柱で支えることがおおむねできるようになったわけですが、完璧に外向きの力がなくなったわけではないので、作りたいもののサイズが大きかったりすると、アーチの外側に逃げる力を抑え込む必要がでてきます。特にアーチの支点が高いところにあると、外側に逃げる力の影響が大きくなります文献5。
ロマネスク様式では例の分厚い壁をつかって支えていたのですが、ゴシック様式では壁や柱そのものは薄い(細い)ままにして、外側からはりで支えるようにしたのです。
 フライングバットレスの図解(画像出典:文献3)
フライングバットレスの図解(画像出典:文献3)
まとめ
ここまでで、ゴシック様式の特徴的な要素として上がられている3つの技術をご紹介しました。パリのノートルダム大聖堂に代表されるような、大きな教会とステンドグラスは、柱とはりで荷重を支えることができるようになった結果、大きな窓を作ることができるようになったことで生まれたんですね。
 ゴシック様式建築の例:フランス・パリのノートルダム大聖堂(画像出典:Ali Sabbagh, CC0, via Wikimedia Commons)。真ん中のバラ窓や、建物右側に見られるように柱の間の壁のほとんどが窓になっている。周りから壁を押さえているはりがフライングバットレス。
ゴシック様式建築の例:フランス・パリのノートルダム大聖堂(画像出典:Ali Sabbagh, CC0, via Wikimedia Commons)。真ん中のバラ窓や、建物右側に見られるように柱の間の壁のほとんどが窓になっている。周りから壁を押さえているはりがフライングバットレス。
12世紀末にゴシック様式が登場した理由
ここまでで、ゴシック様式に使われている技術を見てきたのですが、なぜ12世紀末のタイミングだったのでしょう。実は単なる偶然ではなく、やはり技術革新がかかわっています。それは鉄です文献6。
ヨーロッパでは12世紀ごろから鉄の生産技術に革新が生まれます。カム軸が発明され、水車の回転運動をドロップハンマーの運動に変換することが可能になり、鉄床(かなとこ)での作業が手作業から機械化され、様々な鉄工具の大量生産につながりました。
巨大な石を精度良く切り出せる鉄の工具の普及、石同士を繋ぎ止める鉄芯や鎹(かすがい)、石造建築自体を鉄材によって補強するなど、ゴシック様式の建築には鉄が欠かせない役割を果たしていました。
ロマネスク様式では、小さな石積みをモルタルで接着し、一体構造を作り上げていました。他方、ゴシック様式になると、大きな石材を鉄でつなぎ合わせるという方法に代わっています。鉄の普及という建築部材の革新が、ゴシック様式を生み出す不可欠な要素だったのです。
そのほか参考資料
フランスガイド中村、"【美術解説】 教会建築 「ロマネスク様式とゴシック様式」"、YouTube(参照 2024-01-01)現れた特徴の背景にあったもの、合理的な理由が分かると面白いですよね。最後までご覧いただきありがとうございました。
- 世界史裏探訪、"防御力最強のはずの「城塞都市」が日本で採用されなかった意外な理由"、YouTube(参照2024-12-14)↩
- しかくしか、"インテリアコーディネーター試験【西洋の建築・インテリア① 古代~中世編】"、しかくしか (参照 2025-01-02)↩
- 荘司和樹、"【西洋建築史】ゴシック様式って何?"、note(参照2025-01-03)↩
- ほしがらす、"尖頭交差ヴォールト天井はゴシック様式"、忘れへんうちに Avant d’oublier(参照 2025-01-03)↩
- RYO、"⑧【図解でわかる】ゴシック建築の3つの革新【3/6】"、旅をする記(参照 2025-01-03).↩
- 加藤耕一、"第8回:西洋建築史に見る鉄のテクトニクス"、10+1 website 連載アーキテクトニックな建築論を目指して(参照 2025-01-02)↩